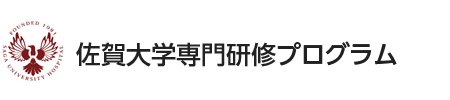
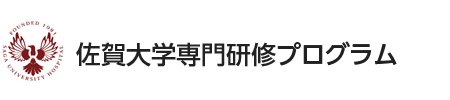
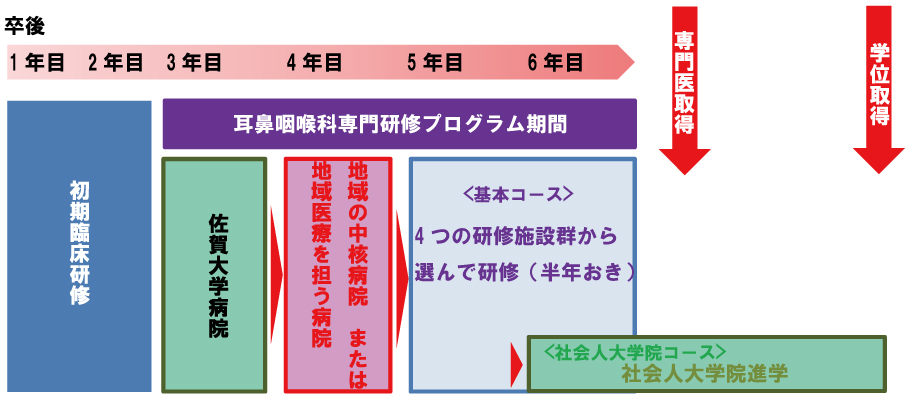
| 名称 | 基準症例数 | 研修年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 難聴・中耳炎 | 25 例以上 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| めまい・平衡障害 | 20 例以上 | 2 | 10 | 5 | 3 |
| 顔面神経麻痺 | 5 例以上 | 2 | 2 | 1 | |
| アレルギー性鼻炎 | 10 例以上 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 副鼻腔炎 | 10 例以上 | 2 | 5 | 3 | |
| 外傷、鼻出血 | 10 例以上 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 扁桃感染症 | 10 例以上 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 嚥下障害 | 10 例以上 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 口腔、咽頭腫瘍 | 10 例以上 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 喉頭腫瘍 | 10 例以上 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 音声・言語障害 | 10 例以上 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 呼吸障害 | 10 例以上 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 頭頸部良性腫瘍 | 10 例以上 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 頭頸部悪性腫瘍 | 20 例以上 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| リハビリテーション(難聴、めまい・平衡障害、顔面神経麻痺、音声・言語、嚥下) | 10 例以上 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 緩和医療 | 5 例以上 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 名称 | 基準症例数 | 研修年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 耳科手術 | 20 例以上 | 鼓室形成術、人工内耳、アブミ骨手術、顔面神経減荷術 | 10 | 5 | 5 | ||
| 鼻科手術 | 40 例以上 | 内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 10 | 15 | 5 | 10 | |
| 口腔咽喉頭手術 | 40 例以上 | 扁桃摘出術 | 15 例以上 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 舌、口腔、咽頭腫瘍摘出術等 | 5 例以上 | 3 | 1 | 1 | |||
| 喉頭微細手術 | 15 例以上 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
| 嚥下機能改善、誤嚥防止、音声機能改善手術 | 5 例以上 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 頭頸部腫瘍手術 | 30 例以上 | 頸部郭清術 | 10 例以上 | 5 | 2 | 3 | |
| 頭頸部腫瘍摘出術(唾液腺、喉頭、頭頸部腫瘤等) | 20 例以上 | 7 | 4 | 2 | 7 | ||
| 名称 | 基準症例数 | 研修年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 扁桃摘出術 | 術者として 10 例以上 | 2 | 7 | 1 | |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 術者として 10 例以上 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 喉頭微細手術 | 術者として 10 例以上 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 術者として 20 例以上 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 気管切開術 | 術者として 5 例以上 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 良性腫瘍摘出術(リンパ節生検を含む) | 術者として 10 例以上 | 1 | 2 | 2 | 5 |